便秘とは
 日本消化器病学会の『慢性便秘症診療ガイドライン』によれば、便秘とは「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義されています。毎日排便があっても便の量が少なかったり、便が硬く出しにくかったり、残便感がある場合は便秘と考えられます。一方で、例えば2-3日ごとの排便でも不快感がなければ、必ずしも便秘とは限りません。
日本消化器病学会の『慢性便秘症診療ガイドライン』によれば、便秘とは「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義されています。毎日排便があっても便の量が少なかったり、便が硬く出しにくかったり、残便感がある場合は便秘と考えられます。一方で、例えば2-3日ごとの排便でも不快感がなければ、必ずしも便秘とは限りません。
便秘は「体質だから仕方がない」と捉えられがちですが、適切な診断と治療により改善が期待できる疾患です。また、背景に大腸がんなど重篤な疾患が潜んでいる可能性もあるため、腸の検査を受けたことのない方は、一度大腸カメラで精査をされておくことをおすすめします。
さらに、慢性的に便秘が持続すると、痔のリスクが増加するのみでなく、心血管イベント(心筋梗塞、狭心症、再灌流、脳梗塞など)のリスクが増加することが知られています。また、近年高齢者の方において認知機能の低下や転倒リスクの増加に関与しているとする報告もあり、注意が必要です。
慢性的な便秘でお悩みの際は、お気軽に当院へご相談ください。
便秘による症状・それに伴う症状について
ブリストル便形状スケール
ブリストル便形状スケールとは、便の状態を示す国際基準です。便が硬いタイプ1~2は、腸内に便が停滞する時間が長くとどまっていた可能性があり、便秘のリスクが高いと考えられます。一方で、タイプ3〜5は排便がスムーズに行われる「正常な便」とされ、排便の状態を評価する目安となります。
| タイプ1 | 切り立った硬い便 |
|---|---|
| タイプ2 | 固いソーセージ状の便 |
| タイプ3 | 亀裂の入ったソーセージ状の便 |
| タイプ4 | 滑らかなソーセージ状の便 |
| タイプ5 | 柔らかく小さな便 |
| タイプ6 | ねっとり、フワフワした便 |
| タイプ7 | 水様の便 |
便秘が生じる原因
便秘は、大きく分けて「機能性便秘」と「器質性便秘」の2つに分類されます。
機能性便秘は、腸のはたらきや排便機能の低下によって生じる便秘のことを指します。便秘の中で頻度が高く、多くの方はこのタイプに該当します。
機能性便秘は以下のように分類されます。
弛緩性便秘
大腸の蠕動運動が低下し、便の通過が遅くなることで便秘をきたします。便が腸管に長時間留まることで水分が過剰に吸収され、便が硬くなって排出されにくくなることも多いです。ご高齢の方、運動不足の方、食物繊維不足・水分摂取不足の方に見られることが多いです。
けいれん性便秘
大腸が過剰に緊張し、収縮することで、便の通過が不規則になり、細切れなコロコロの便が出るようになります。ストレスや自律神経の乱れが関与しているとされます。
直腸性便秘
便意を我慢する習慣や、骨盤底筋の運動障害などで、直腸に便があってもしっかり排出することが難しくなります。女性やデスクワークの多い方に起こりやすいとされています。
一方、器質的便秘とは、肉眼的に確認できる腸の異常や病変が原因で起こる便秘のことを指します。例えば、大腸がんや大腸ポリープにより腸管が狭くなって物理的に便が通りにくくなっている場合や、腸管癒着(手術後や炎症後に腸が周囲の組織とくっついてしまった状態)がある場合、婦人科疾患による腸の圧迫がある場合などが挙げられます。
器質性便秘は、早急な対応が望ましい場合があるため、便秘が継続されている方で、最近大腸カメラ検査を受けておられなかった方には、一度検査を受けていただくことをおすすめします。
便秘の検査・診断
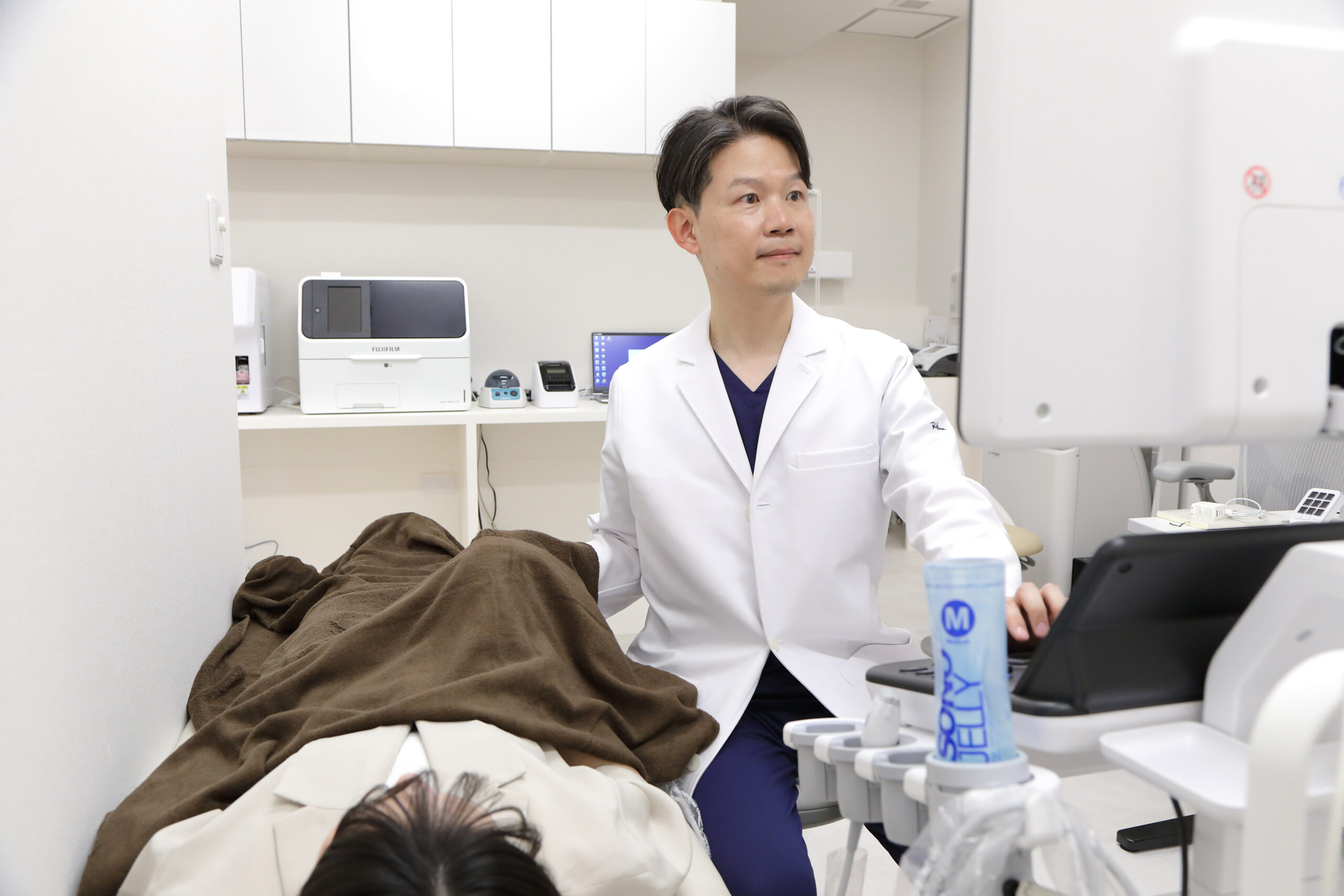 便秘の状況や既往歴、服用中のお薬などについて詳しく問診させていただいたうえで、診察させていただき、その結果を踏まえて、必要となる検査をご提案させていただきます。
便秘の状況や既往歴、服用中のお薬などについて詳しく問診させていただいたうえで、診察させていただき、その結果を踏まえて、必要となる検査をご提案させていただきます。
便秘の評価にあたっては、以下のような検査をご提案することがあります。
血液検査
貧血・炎症などの状態を把握するのに有用です。甲状腺機能低下症では便秘が認められることがあるため、甲状腺機能のチェックをおすすめすることがあります。
腹部レントゲン検査
腸の中に溜まっている便やガスの状態が確認できます。また、腸閉塞の有無を確認するにも有用です。
便秘の治療方法
 機能性便秘と診断された場合には、便秘の改善が期待できる生活習慣を積極的に取り入れるとともに、必要に応じて病状に合わせた薬物療法を行い、便秘に伴う日常生活での苦痛を軽減していくことが大切です。
機能性便秘と診断された場合には、便秘の改善が期待できる生活習慣を積極的に取り入れるとともに、必要に応じて病状に合わせた薬物療法を行い、便秘に伴う日常生活での苦痛を軽減していくことが大切です。
便秘の薬物療法
便秘症の治療で用いられる、効果の高い代表的な薬剤は以下の通りです。
プロバイオティクス
いわゆる善玉菌のことで、「適正な量を摂取したときに有用な効果をもたらす生きた微生物」を指します。プロバイオティクスは、下痢症の治療に用いられることが多いため、「便秘がわるくなるのでは?」と誤解されがちですが、実は便秘に対しても有用であることがわかっています。
善玉菌は以下のような作用機序により、排便機能を改善すると考えられています。
- 腸管内のpHを低下させ、腸管運動を促進する
- 抗炎症作用や免疫調整作用により、腸管運動不全を改善する
- 腸の中で発生するメタンガスを減少させ、便の通過を促す
浸透圧性下剤
浸透圧性下剤は、腸管内の浸透圧勾配を利用して水分分泌を促し、便を柔らかくして排便を促すお薬です。刺激性下剤のような耐性がないので、長期間にわたって安全に使用でき、便秘治療の基本薬のひとつになります。
刺激性下剤
刺激性下剤は、腸を刺激して蠕動運動を促し、排便を促すタイプの下剤です。 即効性があり、便秘改善効果が強力であるため、常用されている方も少なくありません。 しかし、連用により効果が次第に乏しくなる「耐性」が形成されやすく、腸を無理に動かすため腹痛などの副作用が現れやすい下剤でもあります。 そのため、「慢性便秘症ガイドライン2017」でも連用は推奨されておらず、必要に応じて一時的に頓用する服用方法が、安全で理にかなっていると思われます。
上皮機能変容薬
ルビプロストン
小腸粘膜の上皮細胞に存在するクロライドチャネル-2を活性化する薬剤です。消化管内の水分を増加させて便秘を改善します。妊婦の方や妊娠の可能性のある女性の方には使用できません。また、特に若年者の方では服用し始めに嘔気が出ることがあります。
リナクロチド
腸粘膜上皮細胞に存在するC型グアニル酸シクラーゼ受容体というレセプターに作用して、腸管内の水分を増やし、腸管運動を促進することで便秘を改善します。内蔵の知覚過敏を抑制する作用があるため、腹痛を伴う便秘に対して有効な選択肢となります。副作用として下痢が起こりやすい薬ですが、内服時間と食事摂取時間を30分以上あけることで軽減が期待できます。
胆汁酸トランスポーター阻害薬
エロビキシバットは回腸末端の胆汁酸トランスポーターというところを阻害することで、胆汁酸の再吸収を抑制し、大腸内の胆汁酸濃度を高める薬剤です。これにより、大腸の運動と分泌を促進し、排便を促す作用があります。 また、コレステロールを10%ほど低下させる効果も知られています。 副作用としては、腹痛や下痢が起こることがあります。
生活習慣の見直し
便秘解消には、食事だけでなく生活習慣の改善も重要です。
- 朝食を摂取する習慣をもつ
- 朝食後、便意がなくてもトイレに座る習慣をもつ
- 便意を感じたら我慢しすぎないようにする
- 十分な水分を摂取する
- 週に3回以上、軽めの運動(速歩きなど)を行う
食事で注意するポイント
- 規則正しく食事を摂る(特に朝食を摂取するようにする)
- 腸内細菌バランスを整えるため、ヨーグルトや漬物などの乳酸菌を摂取する
- 食物繊維については、便秘の改善に有効とする報告もある一方で、明確な関連が認められないとする報告も少なからずあります。
ダイエットなどで極端な食事制限を行ったり、昼食の摂取量が少ない人は便秘になりやすくなる傾向があります。









